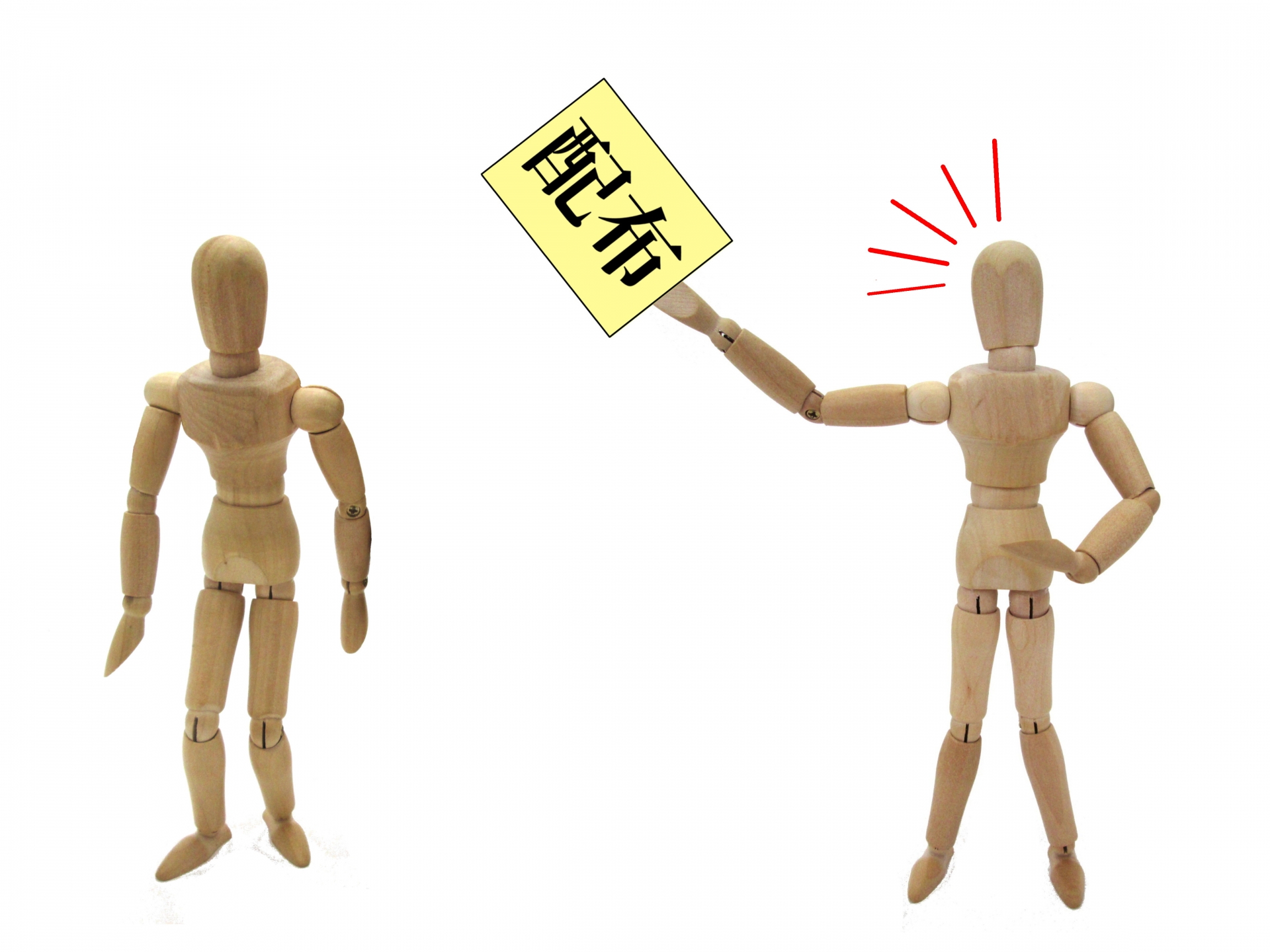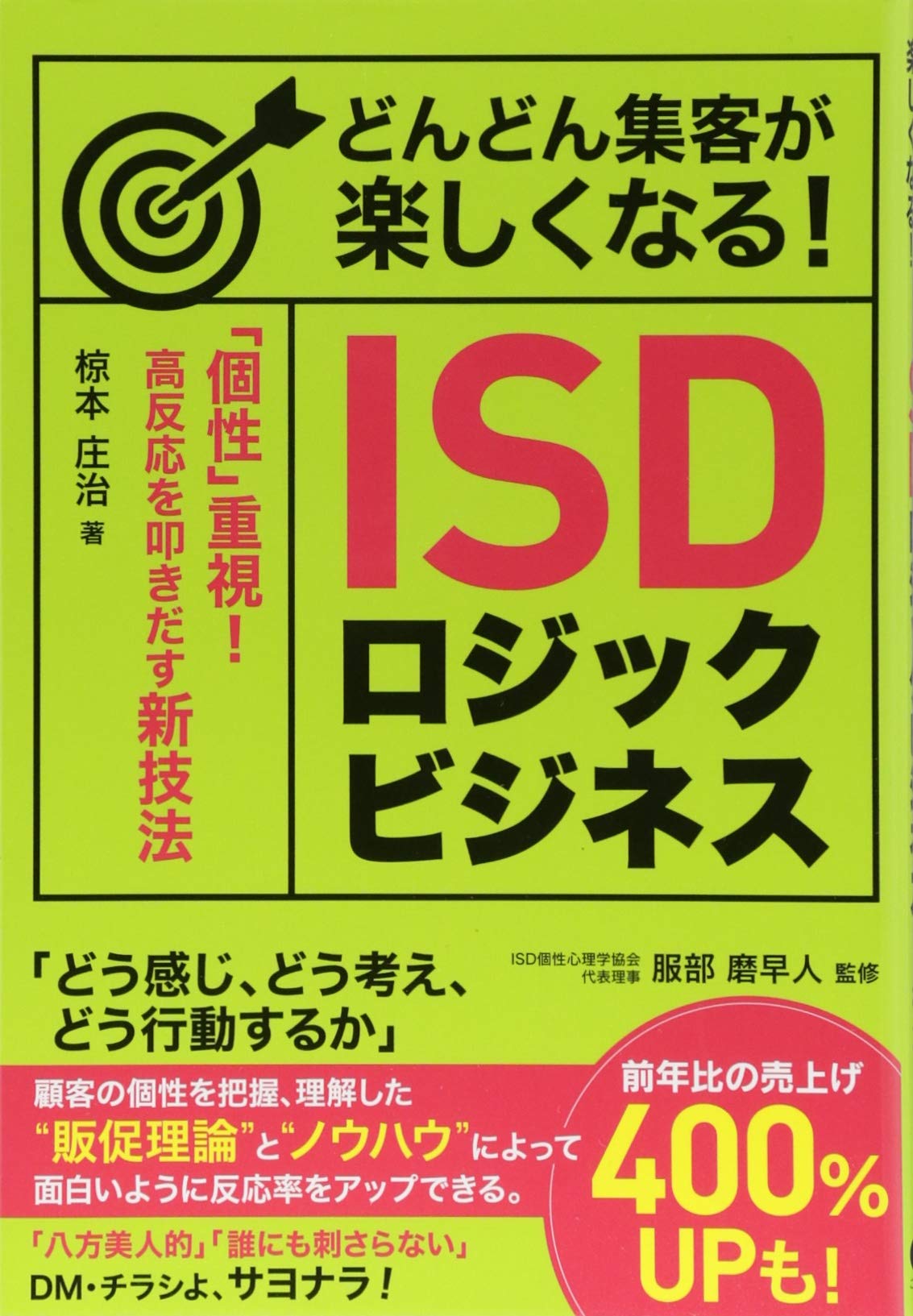チラシの反応率は、年々落ちてきています。
昔は1000枚チラシを配布すれば、3件の注文があったようですが、昨今では10000枚の配布で2~3件といわれています。
しかし、この数字も全業種を平均したときの目安で、購入金額の高い、安いで反応率はずいぶんと変わります。
住宅のような高額なものになると50000枚で5件(0.0001%)あればよい反応率です。0件も珍しいことではありません。
しかし、訴求の仕方やデザインによって、平均以上の反応率を得ることができます。

内容次第で行列はできる!
チラシの反応率はどれくらい
チラシの反響は、業種によって様々です。もっと言えば、チラシを打つ企業によって異なります。
ですから、チラシ集客をする場合、一般論を気にせずに自社のチラシの精度を上げていくことが大切です。
チラシの反応率とは
反応率とは、チラシを打って自社が求める結果に誘導することができた数を言います。
求める結果とは、商品購入、資料請求、問合せ、来店、申し込みなどです。
チラシの反応率は、配布数に対してアクションがあった割合をいいます。
数式にすると「反応数÷配布数」になります。
チラシを10000枚配布して、5件の反応があれば、
5÷10000=0.0005%になります。
先述したように、業種の平均値に捉われることなく、自社のデータを基準にして販促予算を組み立てなければいけません。
例1)スーパーで30万円をかけて5万枚のチラシを配布したとします。平均顧客単価は5000円で粗利益は15%、チラシの反応率が0.002%とします
売上100人×5000円=50万円
粗利益50万円×15%=75000円
225,000円の赤字になります。
チラシを配布しても赤字になるなら、止めた方がよくなります。
チラシの反応率が0.02%であれば
売上1000人×5000円=500万円
粗利益500万円×15%=750,000円
450,000円の黒字になります。
これなら、チラシをつくって配布すれば利益が出ます。
例2)美容室で20万円をかけて2万枚のチラシを配布。顧客単価は10,000円で粗利益は80%、チラシの反響が0.0005%とします。
売上10人×10,000円=10万円
粗利益10万円×80%=80,000円
120,000円の赤字になります。
この場合もチラシは止めた方がよいでしょう。
チラシの反応率が0.005%であれば
売上100人×10,000円=100万円
粗利益100万円×80%=800,000円
600,000円の黒字になります。
これであれば、チラシを打てば打つほど効果があります。
ちなみに
売上25人×10,000円=25万円
粗利益25万円×80%=20万円
25人÷2万枚=0.00125%
これが、チラシを打った時の損益分岐点の反応率です。
これより上回る反応を取ることができるのであれば、チラシは効果的ということになります。

損益分岐点はいくら?
チラシの反応率がよくない理由
冒頭にも書きましたが、チラシの反応率は年々落ちてきています。新聞購読率の低下が主な原因とは思われますが、欲しいものがない、今必要かどうかわからない、お金がないといったことも要因になっています。
新聞購読率の低下
新聞の購読率は年々低下し続けています。
50代以上でかろうじて50%を超えますが、40代では30%前半、30代では20%前半になります。
これからも解るように、30代、40代をターゲットとしている業種は、新聞折込ではなく、他の方法でアプローチする方が賢明です。
欲しいものがない
昔は、手に入れたいものがたくさんありました。しかし、今では、これといって特別に欲しいものがないように思います。
高度経済成長の時には三種の神器ともてはやされた「冷蔵庫」「洗濯機」「テレビ」が欲しいものの代表でした。
それ以外にも、生活が便利になる商品がたくさんありました。
左近では、生活が便利になる商品はどこの家庭にでもあるようになりました。つまり、新しいものを購入するのではなく、動かなくなったから買うという買い替え需要になっています。

特にないね!
必要かどうか気づかない
生活が多様化し、必要かどうか判断できない。つまり、時代の変化が速すぎてわからないというのが正しいかもしれません。
5Gになるといっても、何のことかわからない、スマートスピーカーも同様です。
時代が成熟する前に、先に進んでしまうので全世代に広がらず、一部だけの消費になっていることも要因です。
お金がない
世帯当たりの収入が落ちてきているのも要因です。
50代の平均所得は768万円、40代で686蔓延、30代で558万円、20代で365万円です。手取り額では、50代48万、40代43万円、30代36万円、20代23万円が平均です。
子育て世代の30代の月の手取り額が36万円では、預金するのも難しい額です。50代の手取りが48万円と考えると、子供二人が私学の大学に通っているとすれば、学費だけでも16万円以上かかるので、経済的な余裕はありません。

ないんだよ!
反応率を上げるためには
このような状態ですから、ターゲットにしっかりした情報を届けなければ反応は取れません。
ターゲットを明確にする
誰に届ける情報なのかを明確にします。30代の男性といった抽象的なものではありません。
例えば、35歳男性、子供が2人(幼稚園児と小学低学年)、大手企業に勤めていて年収は700万円、車はワンボックスタイプ、趣味は釣りという具合に具体的にします。
何を届けたいか
ターゲットに届けるものは何なのか、そして、それは、彼らにどのように役立つのかを考えます。
そして、考えたことを紙面に落とした時、どんな訴求すればよいのかを考えればいいのです。
どんなメリットがあるか
訴求内容を考えるときに欠かせないのがベネフィットです。
その商品を購入すれば、どんなにいいことが起こるのか、生活が楽になるのかを、思いつく限り書き出してみることです。
ジャパネットタカタでは、売り出す商品を従業員に使ってもらうそうです。そして、どのような使い方をしたかのをアンケートを実施して、意見を吸い上げるそうです。
ですから、メーカーが想定していないような使い方まで出てくるのです。これらが、ベネフィットになり、お客様は「それは便利だ!」と、商品を購入してくれるのです。

たくさんあるはず!
配布エリア決めと配布頻度を上げる
新聞折込の反響が落ちているので、多くの方に情報を届ける場合は、ポスティングが有効になります。
しかし、ポスティングも単に配布するだけではなく、綿密な計画が必要です。
エリアを分ける
まずは、配布エリアを決めることです。
これが決まると、配布エリアを分けるのです。その分け方は町名ごとに分けます。
例えば、大阪市西区本町であれば、本町は1丁目から4丁目までありますので、本町1丁目、本町2丁目…というように〇町〇丁目ごとに分けるのです。
なぜなら、市町村の人口統計表がこのように分かれているので、これに合わせたエリア分けをしておくと、データ分析をするときに便利だからです。
重点地域を決める
エリア分けができれば、重点地域を決めます。
通常は、店舗から近い地域です。次は、お客様が多い地域順、そして、競合店とエリアの重なる地域です。
これらを決めたうえで、チラシの投下回数を決めていくのです。
まんべんなくエリアに1回ポスティングするのと、そのうえで、重点エリアにどのようにポスティングするのかを決めて実施するのとでは、どちらが反応が高いのかは察しが付くと思います。
重点地域に対して配布数を決める
重点地域を絞って配布するとは
- イベント10日前に全体にポスティングする
- イベント5日前に店から近い地域にポスティングする
- イベント3日前に競合店とエリアの重なる地域にポスティングする
- イベント1日前に全体にポスティングする
というような配布計画を組んで、配布すると反応率も上がります。

配布計画も大切です!
今後のチラシの考え方
よりチラシの反応率を上げるためには、ターゲットを絞るだけではなく、絞ったターゲットをさらに個性別に分けることです。
人は、商品を購入するとき大きく分けると3つの分類に分かれます。
- 価値を感じて行動するタイプ
- みんなが使っていると安心するタイプ
- 有名人やブランドに惹かれるタイプ
このことを理解していると、チラシに作り方は根底から変わります。
どれかのタイプに焦点を合わせてチラシを作成すると、今までではなかったような反応があります。
商品にもよりますが、私なら3つのタイプのチラシを作成して配布します。
かつて、貴金属の買取店で、「価値を感じて行動するタイプ」に向けたチラシを作成したことがあります。
結果をいうと、今までにチラシの1100%の来店がありました。数字でいうと、4組が44組になったのです。
これらの詳しい情報は、私に著書「どんどん集客が楽しくなるISDロジックビジネス」に書いています。ご興味のある方は、ご一読ください。
まとめ
今は、新聞購読率の低下に伴い、新聞折込の反響は落ちています。また、欲しいものがないとかお金がないという理由で消費が落ちこんでいるのも事実です。
それでも、気づかせることによって購入する人はまだまだいます。そのためには、詳細なターゲットを決めて、さらに3つのタイプに分けて、訴求することが大切です。
また、配布エリアを決め、重点地域を決めて配布の計画を立てることです。