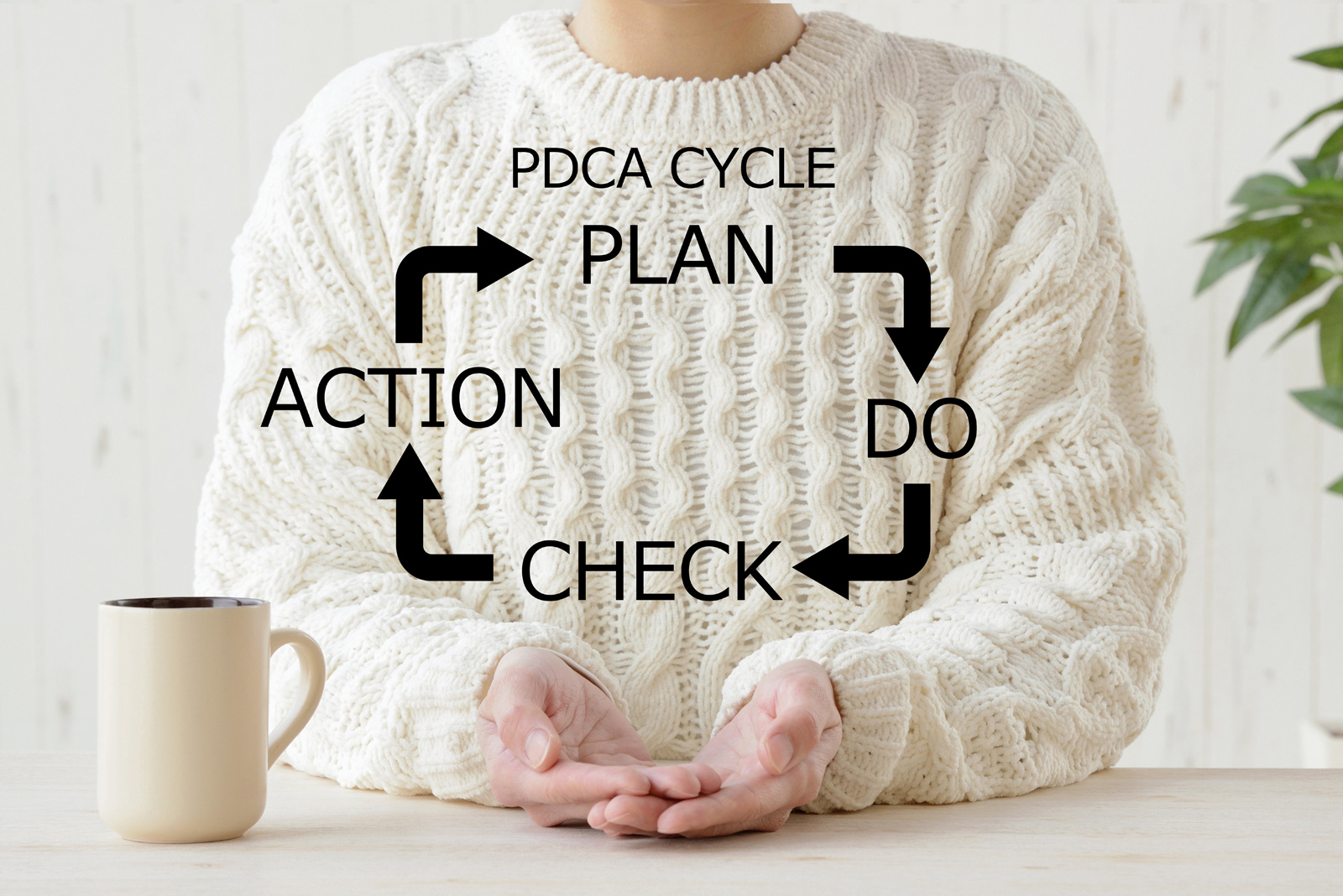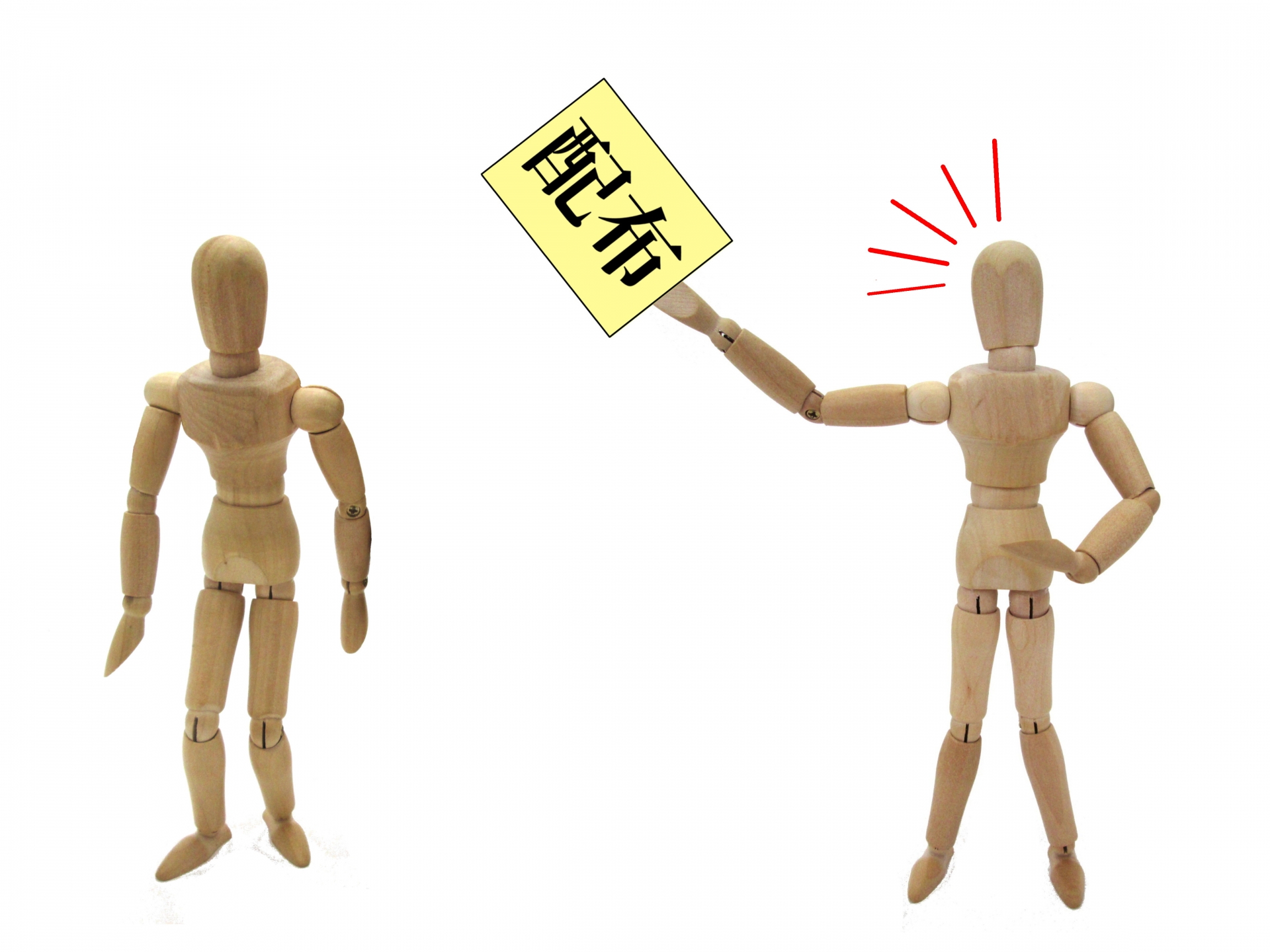タウンプラスってご存知ですか?
日本郵便が提供しているサービスです。指定した地域にハガキや封書を配布してくれます。
ポスティングの場合は、「投函禁止」「ポスティング禁止」と書かれている集合住宅(マンション)のポストに、ポスティング業者などが、チラシなどを無断で入れると不法侵入ということで罪に問われます。
しかし、日本郵便に依頼してポスティングした場合は、罪に問われることはありませんので、このようなサービスを利用するのも方法のひとつかもしれません。

いいサービスじゃないの?
タウンプラスって何?
タウンプラスとは、ハガキや封書を指定した地域に、日本郵便が投函してくれるサービスです。地域を指定するだけなので、宛名書きがなくても投函できます。
利用の流れは以下の通りです。
1.配達地域にある郵便局に相談に行って、配達する地域を決めます。その際に、希望地域に必要な通数を確認してください。「〇〇町」「〇〇丁目」単位で配達地域を指定できます。また、マンションの場合は、マンション名を指定して配達することもできます。
※近くの郵便局が解らない時は下記から検索してください。
http://www.post.japanpost.jp/shiten_search/
2.相談が終わったら、「タウンプラス差出計画書」と「差出内訳票」「タウンプラス差出票」を作成します。「タウンプラス差出票」は配達する郵便局ごとに、2部作成する必要があります。
これらは、配達予定日の前日から起算して14日前までに、タウンプラスを利用する郵便局に提出が必要です。
「タウンプラス差出計画書」と「差出内訳票」のテンプレートは以下よりダウンロード
できます。
https://dmfactory.biz.post.japanpost.jp/townplus/keikaku.pdf
「タウンプラス差出票」のテンプレートは以下よりダウンロード
できます。
https://dmfactory.biz.post.japanpost.jp/townplus/sashidashi.pdf
3.配達地域ごとにタウンプラスを区分して、その上に配達地域(〇〇1丁目、〒111-1111)と配達担当郵便局と通数を記入した用紙を添付してください。
4.配布物を配達地域の郵便局に持参してください。
以上が、申し込みの手順になります。
郵便番号ごとに、結束したりしなければいけないので面倒ではありますが、届けたい地域に、確実に届けることができます。

仕分けも手間ね!
地域密着型のお店には効果的!
では、どのようなときにタウンプラスを利用すれば有効なのでしょうか?
主には地域密着型の商売をしている方の利用をお勧めします。特に「〇〇丁目」まで絞りたいときには有効です。
「ポスティングすればいいじゃないか」という声もありますが、ポスティングは「立川反戦ビラ事件」で、集合住宅への住居侵入罪の容疑で配布業者が逮捕・起訴されています。
この事件後、ポスティングを止めた大手企業はたくさんあります。また、地域の情報誌を配布している出版社も「ポスティング禁止」の貼り紙のあるマンションへの配布は控えているので、情報誌の広告もすべての人には届いません。
ですから、地域密着型で、商圏の人すべて、または、商圏の一部の住人に届けたい企業は
利用するといいでしょう。
新規出店の場合は、折り込みチラシでオープンの告知をする企業が多いのですが、折り込みチラシの購読率は、50歳以上は50%を超えますが、40歳代では30%前半、30歳代は20%前半の購読率です。
40代、30代をターゲットとする場合は、折り込みチラシでは一部のターゲットにしか届きません。
名簿がない企業にも有効です。
顧客名簿があれば、ニュースレターやDMを送ればいいのでしょうが、名簿がない場合は、新規出店の場合と同様、折り込みチラシも地域情報誌への広告も必要ですが、有効な手段とは言えません。
ということで、「タウンプラス」は地域の全住人に届けることができる有効な手段だといえます。

地域が決まっているときに有効ね!
タウンプラスのディメリット
タウンプラスのディメリットは、
1.500通以上でないと配達できない
2.手続きが面倒
3.納期がかかる
4.配布物の仕分けが手間
5.一通の料金が高い
H3 1.500通以上の配達
〇〇丁目という細かい部分まで詳細に分けるので、必然的に数量が少なくなります。「〇〇町1丁目」ならば通常30番地くらいです。数が少なすぎると手間ばかりが増えるからです。
ですから、日本郵政としては、少なくとも500通以上にまとめて欲しいのです。
2.手続きが面倒
先ほども述べましたが、「タウンプラス差出計画書」と「差出内訳票」「タウンプラス差出票」というものを提出しなければならず、町名や丁名の世帯数を調べる手間がかかります。
3.納期が長い
2の書類を配達予定日の前日から起算して14日前までに、郵便局に提出しなければならず、早い段階から配布計画を立てたにもかかわらず、配達されるまで日時がかかります。
4.配布物の仕分けが手間
配布物を郵便局に持ち込む際、丁名ごとに仕分けしなければならず、大変手間がかかります。配達数が多ければ多いほど手間がかかります。
5.料金が割高
料金はDMと比べると安いのですが、ポスティングと比較した場合、2倍以上の割高になります。ポスティングが10円くらいなのにタウンプラスは25~53円(個数や形状による)になります。
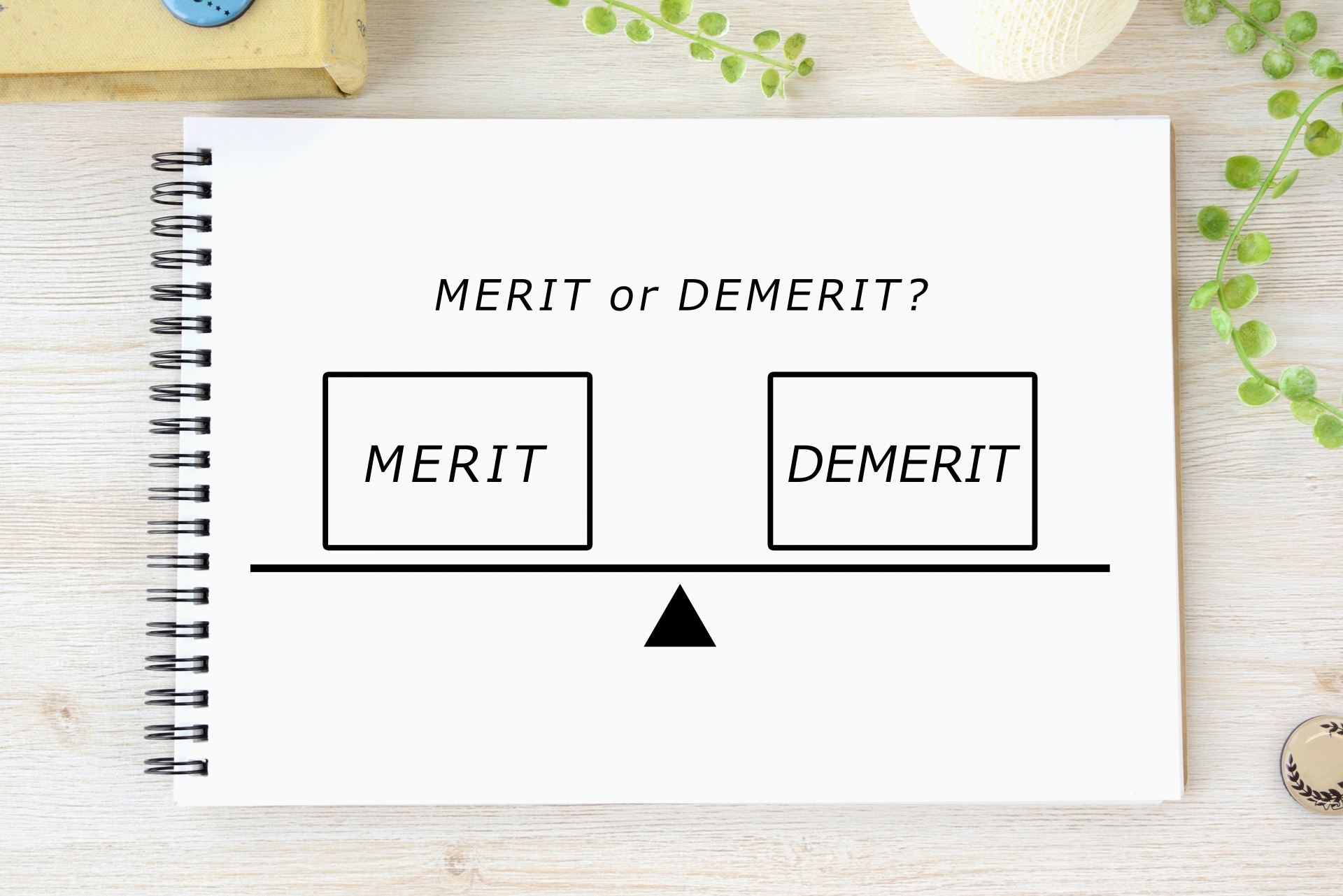
メリットもディメリットもあるね!
タウンプラスとタウンメールの違いは?
タウンプラスの他にもタウンメールというのがあります。こちらも地域を指定して配達できる郵便局のサービスです。
タウンメールとの違いは、重さ(g数)と数量と納期の違いです。
重さ
タウンプラスは、重さの明確な規定はありません。
しかし、タウンメールは重さの規定があります。
25gまで29円
25g~50gまで42円
50g~100gまで56円
数量
タウンプラスは500個以上ですが、タウンメールは指定がありません
納期
タウンプラスは、差出希望日の14日以上前ですが、タウンメールは、最短3~5営業日になります。
まとめ
地域戦略を立てる上で、タウンプラスは効果的な配布方法と言えます。
世代別ターゲットを絞る場合は、役所の人口統計表と比較すれば、どの地域にターゲット層が多いのかもわかりますので、無駄のない配布ができます。
しかし、料金が25~53円とポスティングにと比較すれば、約2倍以上の開きがあります。まずは少数で試した反応を基に、どう使えばいいのかを検討することが大切です。