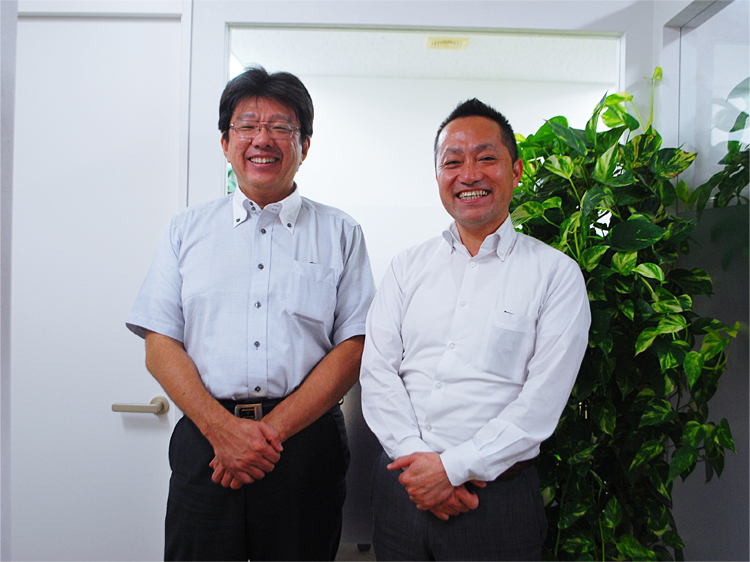株式会社アーストレック
代表取締役 原田 智樹さま
アーストレックは、平成9年に設立された会社です。プレゼンテーションツール、デジタルステーショナリー、モバイル周辺機器などを製品の企画から開発、製造までを手掛けておられます。ロゴマークの三本ラインには「空」「大地」「海」という意味があります。「空」は高い志、「大地」はフロンティアスピリット、「海」は創造力を表しています。
ホームページ:http://www.earth-trek.co.jp
レーザーポインターを主力に販売させていただいています。

椋本:販売ルートについて教えていただけませんか?
原田:主には、医薬品メーカーと電子文具メーカーです。医薬品メーカーには、メディカルコミュニケーションツールを販売させていただいています。電子文具メーカーには、弊社で企画製造した商品を卸しています。
椋本:かつては医薬品メーカーにノベルティーを販売していたことがあるのですが、オリジナリティーを求められるものばかりでした。今はどうですか?
原田:それは同じです。オリジナルのものしか購入してくれないですね。今でこそ一般的になったレーザーポインターですが、創業当時は、ほとんど認知されておらず、プレゼンテーションの時は、長いスティックを使っていたのです。このレーザーポインターを医師のプレゼン用として使ってもらうために、医薬品メーカーに持ち込んだのです。
椋本:そこからが製薬企業向けの事業の始まりですか?
原田:そうですね。今でもレーザーポインターは主力の商品ですが。その後、メディカルコミュニュケーション分野を開拓して来ました。現在直接、間接関わらず、多くの国内、海外医薬品メーカーの取引がありますので、引き合いがありますね。
椋本:基本的なことをお聞きするのですが、レーザーポインターは自社で製造されているのですか?
原田:工場は、深圳と広州の中山にあります。
椋本:協力工場ではないのですね。自社工場ですね。
原田:そうです。最初は台湾に工場を作ったのですが、人件費や物価の高騰などもあり生産性が合わなくなったので、深圳に拠点を変えたのです。ここでは、製品開発会議から始まって、試作品を作り改良を加えて生産する一貫性のある工場です。香港は流通の中心としての位置づけです。世界企業が集まるエレクトロニクスの展示会もあるので、こちらへの出展もしています。
レーザーポインターは、お客様の要望をお聞きし形に変えました。

椋本:製品開発はどのようなされていますか?
原田:製品開発には2通りあります。1つは、ODMです。お客様からの要望をお聞きし、それを製品という形に変えていくもの。2つ目は、こんなのあれば便利かな、という視点で開発していくというものです。
椋本:レーザーポインターはどちらの視点で生まれたのですか?
原田:後者ですね。お客様は展示会でご来場頂いたり、雑誌記事を読んで頂いて声をかけて頂いたり、それが電子文具メーカーさんであり、医薬品メーカーさんだったんですよ。
椋本:ホームページにある製品などは、個人への通信販売とかされないのですか?
原田:電子文具メーカーにも納入していますので、自社での個人売りは考えていません。ですから商品はB2Bでしか販売できないのですよ。
香港に進出したのも販路拡大のためでした。

椋本:香港、中国に進出された時、仕入れ先や販路の開拓はどのようにされたのですか?
原田:当時は、インターネットがなかったですから、現地の電話帳を調べて電話しました。日本から来ているので工場視察をさせて欲しいと、お願いしていました。有効なのは展示会でしたね。カタログを収集して、ここと思う企業に電話をしてまずは仕入れ先工場を開拓しました。
椋本:ところで、大阪、東京、深圳、香港とありますが、従業員数は何人くらいなのですか?
原田:日本で12名、中国は80名ですね。中国は、製品開発系のエンジニア集団です。もの造りの人材が豊富にいます。
椋本:中国は開発系なのですか?通常、中国進出は逆ですよね。開発は国内で、生産を海外でというのがセオリーだと思っていました。
原田:本来ならそうなのですが、開発系のエンジニアが日本国内にいなかったのです。募集しても人は集まらずで、どうしようかと悩んだあげく、中国で開発系エンジニアを探そうと決めたのです。 マーケティングと基礎需要の市場調査は日本で、開発は海外でという構図です。
椋本:言葉の壁もあるわけですから、思い切った決断ですね。
原田:その時は、それしか選択肢がなかったのです。でも、今は、よかったなと思っています。エンジニアが不足していても募集を出せばすぐに応募がありますからね。
椋本:では、生産はどうしているのですか?
原田:試作生産を含む数千個の小ロットの注文は、自社工場で賄いますが、何十万、何百万個という大型注文に関しては、外部に協力会社を持っています。
椋本:アップル社のような形ですかね。試作品や小ロットは自社で賄い、大量生産するものは外部に出す。
原田:そうですね。自社ですべてを生産するとなると今の人数の5倍以上は必要になります。そうなれば、小回りが利かなくなり、せっかくの開発系エンジニアを活かすことができなくなってしまいます。
椋本:そうですね。開発に力を注いで、販路を拡大する方が効率的にもいいですよね。
原田:そうなんです。香港に進出したのも実は販路拡大のためなのです。先ほども言いましたように、国内ではB2Bでしか販売できません。しかし、同じ商品を海外で販売するのはOKなんですよ。今では、香港からアメリカ、ヨーロッパへ販売しています。
椋本:販路拡大にともない売上も右肩上がりですか?
原田:そうですね。日本より売上は伸びています。
実践しながら修正してきて、生まれた事業があります。

椋本:今の仕事をされるきっかけは何だったのですか?
原田:創業するときに、海外でも通用するような仕事がしたという思いだけがありました。だから、海外への視察ツアーにも参加してみて回りましたね。その中で、カンボジアのハンディークラフトセンターに行ったんですよ。地雷でハンディを負ってしまった子供たちが紙で作ったものを売っているのを見て、社会貢献にもなるNGOをやろうかとも考えましたが最終的にはビジネスを選びました。国境に囚われる事の無いビジネスで、世界の人とつながりが持てれば幸せだと考えたのです。また、国際交流を通じて少しでも国際社会に貢献したいという思いがありした。
椋本:なるほど。
原田:それも偶然でね。台湾の展示会でレーザーで距離を測るモジュールを見ていたのです。その時に、これを応用できないかなといろんなものを調べたところ、サクラクレパスさんがレーザーポインターを作っていたのですが、ほとんど売れていなかったのです。しかし、直感的に売れるんじゃないかと思い、試作を作り展示会で出展したところ結構売れたのが始まりです。これが今でも、弊社の主力商品になっています。
椋本:原田さんのガッツはどこから来ているのですか?
原田:私は、左脳派ではなく右脳派なんですね。将来このようになっていたい、こんな会社にしていたいというようなことが頭の中に鮮明にあるんですね。そして、そのようになるためにはどうしたらいいのかを考えています。
椋本:後は、考えたことを実践するということですか?
原田:そうです。実践しながら修正していくのです。その中で生まれてきた事業があるのです。メディカルコミュニケーションと言っていますが、医療現場で役に立つ製品の開発です。
社会貢献のできる事業としてメディカルツールを伸ばしていきたいと思います。

椋本:医療現場での製品となると大掛かりな機械をイメージしますが、医療機器なのですか?
原田:そうではないんです。医師や看護師の手を助ける補助具のような製品です。例えば、糖尿の人がいて、自身でインスリンを打たなければならなくなったとしますよね。その場合、看護師さんが手取り足取り使い方を教えなければならないでしょ。そうなると、他の業務ができなくなったり、次の患者さんを待たせることになりますよね。これの代わりと言っては何ですが、インスリンを打つための自主学習動画を作るだけでなく、インスリンを簡単に打てるための補助具も開発するのです。病院だけではなく、調剤薬局でも使われ始めています。
椋本:それは、便利ですね。
原田:このような商品をいくつも開発し、医薬品メーカーに持ち込むと医師や病院に紹介してくれて採用されているんですよ。これを今後の事業の一つに成長させていきたいと思っています。
椋本:今後の展望はどのように考えておられますか?
原田:やっぱり、メディカルツールを伸ばしていくことですね。医療にかかわる人の手を助けることができますし、患者さんにとっても分かりやすくなります。そういう意味では、社会貢献のできる事業であると思いますからね。
椋本:これから先が楽しみですね。